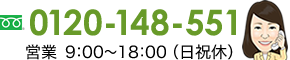京都市伏見区にて、9寸京都型のお墓を建立。将来の管理を考えたお墓づくり
こんにちは。京都市、亀岡市、宇治市、向日市、長岡京市、八幡市をはじめとした、京都南部にてご対応させていただいております、石材店かわむらの川村です。京都市伏見区にて9寸京都型のお墓を建立させていただきましたので、お墓作りと工事の様子をご紹介いたします。
 伏見区 京都型9寸建立
伏見区 京都型9寸建立
ホームページをご覧になったお客様からお墓の建立をご相談いただきました。墓地はすでにお持ちでしたので、現地を確認してご提案をさせていただきました。当社からは車で30分ほどのところでした。
 こちらが建立場所です。お住まい近くの伏見区の墓地で、現地でお会いしてご希望を伺いました。「周りにあるお墓と調和のとれたものにしたい」とのご希望をいただき、細部はお好みの寸法を具体的にご指示いただきながら設計しました。建築関係のお仕事をされていて、芝台の高さを少し高くしたり、一部を広めにしたりと、具体的なご指示を図面に反映させています。2,3回図面をやり取りして、ご納得いただける形に仕上がってから工事に取りかかりました。
こちらが建立場所です。お住まい近くの伏見区の墓地で、現地でお会いしてご希望を伺いました。「周りにあるお墓と調和のとれたものにしたい」とのご希望をいただき、細部はお好みの寸法を具体的にご指示いただきながら設計しました。建築関係のお仕事をされていて、芝台の高さを少し高くしたり、一部を広めにしたりと、具体的なご指示を図面に反映させています。2,3回図面をやり取りして、ご納得いただける形に仕上がってから工事に取りかかりました。

工事開始です。まずは土を掘り下げ、地固めをしました。

しっかり地固めしたら、一番下の芝台を据え付けるため準備をします。

手前と側面の石を耐震ボンドで接着します。
 接着面にはボンドを使用して、角はL字の耐震金具を取り付けて固定します。耐震ボンドとあわせて、石が開いたりズレたりすることを防止します。
接着面にはボンドを使用して、角はL字の耐震金具を取り付けて固定します。耐震ボンドとあわせて、石が開いたりズレたりすることを防止します。

芝台の設置が終わりました。次は、台石を順に設置していきます。

芝台の上に下台を設置しました。手前の開口部から納骨をします。京都型はここに供物台を設置して納骨口をふさぎます。
 香炉を設置します。当社では、このように香炉をボンドで石に接着します。
香炉を設置します。当社では、このように香炉をボンドで石に接着します。
 下台の上に上台を据えて、香炉を設置しました。長い年月使われても、香炉がガタついたり落下したりしないように接着しています。
下台の上に上台を据えて、香炉を設置しました。長い年月使われても、香炉がガタついたり落下したりしないように接着しています。

花立を設置しました。花立も香炉と同じようにボンドで接着しています。京都型は花立の高さがあるので、お参りの時にぶつかって倒れてしまわないように、ほとんどの石材店で施工の際に接着しています。

納骨室の入り口の蓋になる供物台を置いて、ステンレスの花筒等を設置したらお墓の完成です。

京都型9寸の和型墓石です。9寸はお墓のサイズで、棹石の幅が9寸(約27cm)という大きさです。9寸は京都市内のお墓としては少し大きめの部類になります。「将来お掃除や管理がしやすいように」というご意向を受けて、お墓の後ろにも入りやすくするなど、その思いを設計に反映しました。

棹石正面はご家名で、左側面に建立年月と建立者の方のお名前が彫刻されています。上台は棹石手前に水溜めを設けています。基本的に、お水・お線香・お花は用意されるのが一般的なので、水溜めを設けない場合はコップを置くなどしている方もおられます。

右側面はご戒名が彫刻されています。お隣のお墓とも調和のとれた、バランスの良いお墓に仕上がりました。
 実は今回、お墓が完成する前にお施主様がお亡くなりになり、ご家族様にお引き渡しをさせていただきました。ご家族皆様でお越しくださり、お父様から伺ったご要望やお打ち合わせをした内容などを息子様にお話ししました。詳しい内容は息子様も初めてお聞きになったようで、「そんな話をしてたんですね」「話が聞けてよかったです」とおっしゃってくださいました。このたびのお墓の建立にあたり、お父様から当社にご縁をいただきましたこと、大変ありがたく思っております。ご冥福をお祈り申し上げるとともに、お父様が将来の管理のことも考えて作られたお墓をご家族皆様で末永くお参りいただけますよう願っております。お墓のことで何かございましたら、何なりとご相談くださいませ。
実は今回、お墓が完成する前にお施主様がお亡くなりになり、ご家族様にお引き渡しをさせていただきました。ご家族皆様でお越しくださり、お父様から伺ったご要望やお打ち合わせをした内容などを息子様にお話ししました。詳しい内容は息子様も初めてお聞きになったようで、「そんな話をしてたんですね」「話が聞けてよかったです」とおっしゃってくださいました。このたびのお墓の建立にあたり、お父様から当社にご縁をいただきましたこと、大変ありがたく思っております。ご冥福をお祈り申し上げるとともに、お父様が将来の管理のことも考えて作られたお墓をご家族皆様で末永くお参りいただけますよう願っております。お墓のことで何かございましたら、何なりとご相談くださいませ。
京都市内でのお墓の建立に関する記事
●国内加工の愛媛県産大島石の五輪塔を建立。京都市上京区寺院墓地
●地覆石をバランスよく設置したインド産黒御影石の洋型墓石を建立。上京区寺院墓地